一条兼定(四代)
| トップページ | 歴史ロマントップページ |
■ 一条兼定(1542-1585)
天文18年(1549)父を喪った兼定は、わずか7歳の幼児ながら公家大名土佐一条氏の家督者として動乱の世に身を処せねばならなかった。それでも従祖父(祖父房冬の弟京一条家の当主)准三宮房通の楢子となったことで、天文20年10月、9歳で正五位下に直叙され、12月元服と同時に左近衛少将に任官、ついで従四位上に越階、翌21年7月、従三位と、とんとん拍子に昇進している。官位の昇進は公家の子としては喜ばしい事であっても、戦国の世の大名としての実力を加えるものではなかった。果たして、兼定が15歳になった弘治3年(1557)2月、吾川郡の本山茂辰が、一條氏の支城となっている森山、秋山のニ城(共に吾川郡内)を攻め取り、つづいて仁淀川を渡って高岡郡の蓮池城を奪った。これは当時一條氏が伊予に出兵している隙を狙ったものである。
一条氏の伊予出兵は兼定の母の兄であり、妻の父でもある豊後の大友義鎮(宗麟)に協力したものであった。大友氏の西伊予侵攻は天文年間から義鑑、義鎮の二代にわたって繰り返され、その都度一条氏も出兵している。永禄元年(1558)には法華津、御庄など西伊予の諸城を攻め落とし、仝3年(1560)には宇和郡の首将西園寺氏を降し、その麾下随一の勇将土居氏の立間郷石城をも落城させた。かくて永年の望みを達した大友軍は豊後に引き上げ、宇和郡一円は一条氏の支配下に入った。この年一条氏は本山氏に奪われていた蓮池城のにも奪回にも成功している。
しかし一方では長岡郡の長宗我部元親が土佐、吾川郡の二郡に勢力を振るう本山茂辰(妻は元親の姉)を攻め、土佐郡の諸城を次ぎ次ぎに落とし、後退する茂辰を追うて本領本山の奥地に追い詰めて降伏させた。その間、永禄6年(1563)には吾川郡南部の弘岡城を吉良氏から奪っている。かくて土佐の中央部を手中に収めた元親が次に狙うのは東部安芸郡の安芸氏と西部の幡多、高岡ニ郡を領する一条氏でなくてはならない。
元親は先ず永禄12年(1569)8月、大軍を発して安芸城を猛撃し、城主安芸国虎を自殺させた。国虎は自刃に先立ち夫人を一条氏に送り届けた。(夫人は兼定の叔母とも姉妹ともいう)安芸氏の敗戦が兼定に強い衝撃を与えたのはいうまでもない。しかも、それから3ヶ月後の11月には、元親の弟で吾川郡弘岡城主吉良親貞のために、先年本山から取り返したばかりの高岡郡蓮池城を奪われた。この蓮池城奪取は元親の意にそむいて親貞が独断強行したものというけれど、元親の深慮遠謀によるものであることは、親貞から蓮池城奪取の進言を受けたとき『大恩ある一条家の城を取るなど以ってのほかでだ』といいながら、「天罰は拙者が引き受けるから万事まかせられよ。」という親貞の言葉を黙認していることで明らかである。
第二の矢は姫野々城を本拠として勢力を張る一条麾下の津野氏に向かって放たれた。元親は先で津野定勝に対し、一条氏攻撃の協力を求めたが、佐田勝はこれを拒絶した。しかし家臣は元親に降ることを決議し、主君定勝を伊予に追放して、その子勝興を立て元親の娘を妻に乞うて降った。
高岡軍久礼城主佐竹氏は一条氏譜代の老臣でありながら元親を恐れて内通し、一条氏への義理に形式的な一戦ののち元親に降った。その後、間もなく仁井田郷の諸将を降し高岡郡を完全に手中に収めた元親は、いよいよ一条氏の本拠幡多郡と堺を接することになった。かくて一条氏に不安の感を与えながら元亀2年の冬、元親は一先ず兵を引き上げて岡豊に帰城した。このような国内の不穏につけこんで、元亀3年には伊予の西園寺氏が幡多に侵入してきた。一条氏は大友の援軍と共にこれを撃破した。
明けて元亀4年(1573)6月7日、兼定は左近衛中将に転じ、同月19日には権中納言に昇進した。この昇進は天文21年(1552)10歳で従三位に叙せられて以来、実に21年ぶりのことで、官位の昇進の早い一条家の人としては異例なこといえる。このように昇進がおくれたについては次のようなことが考えられる。
兼定が従三位に叙せられてから2年後の天文23年(1554)には、義兄である京一条家の当主関白兼冬が26歳で急死し、兄のあとを継いだ異母弟の内基は未だ9歳の幼児であった。さらにまた2年後の弘治2年(1556)には兼冬内基の父であり、兼定にとっても従祖父で養父となっている准三后房通が死ぬなどの不幸が続いて、一条家の冬の時代であった。そうしたことで遠国土佐に居る兼定の昇進運動が忘れられていたのではあるまいか。
久しぶりの兼定の昇進と時を同じゆうして京都から内基が中村に来ているが、これは一条家も再び春の時代を迎えたことを物語るもので、吉報をもたらし傍々義兄の兼定に面会のためではなかったろうか。内基は兼定より5歳年少で当年25歳であったが、摂家一条家の当主として正二位権大納言で官位は兼定より高く、その後間もなく内大臣、右大臣、左大臣を歴任して関白にまでなっている。
ここで兼定に同情的な見方をすれば、兼定は7歳で父房基に死別し、従祖父房通の楢子となっているので房通の実子兼冬の義弟ということになる。兼定という名もおそらく兼冬の弟であるためにつけられたものであろう。兼冬が死んだ時内基は7歳、兼定は13歳であった。内基が生まれていないか乳児であったなれば、兼冬のあとを継いで兼定の一生は大きく変わっていたかもしれない。こうした点からも、兼定は不運な星に生まれ合わした人であったといえる。
それはともかく、元亀4年(7月28日天正と改正)刃兼定にとって、喜びの年であったと同時に悲しみの年でもあった。31歳の若さで出家(隠居を意味する)しなければならなかったからである。しかし、その理由は不明である。
■ 一条兼定軍用金伝説の古銭
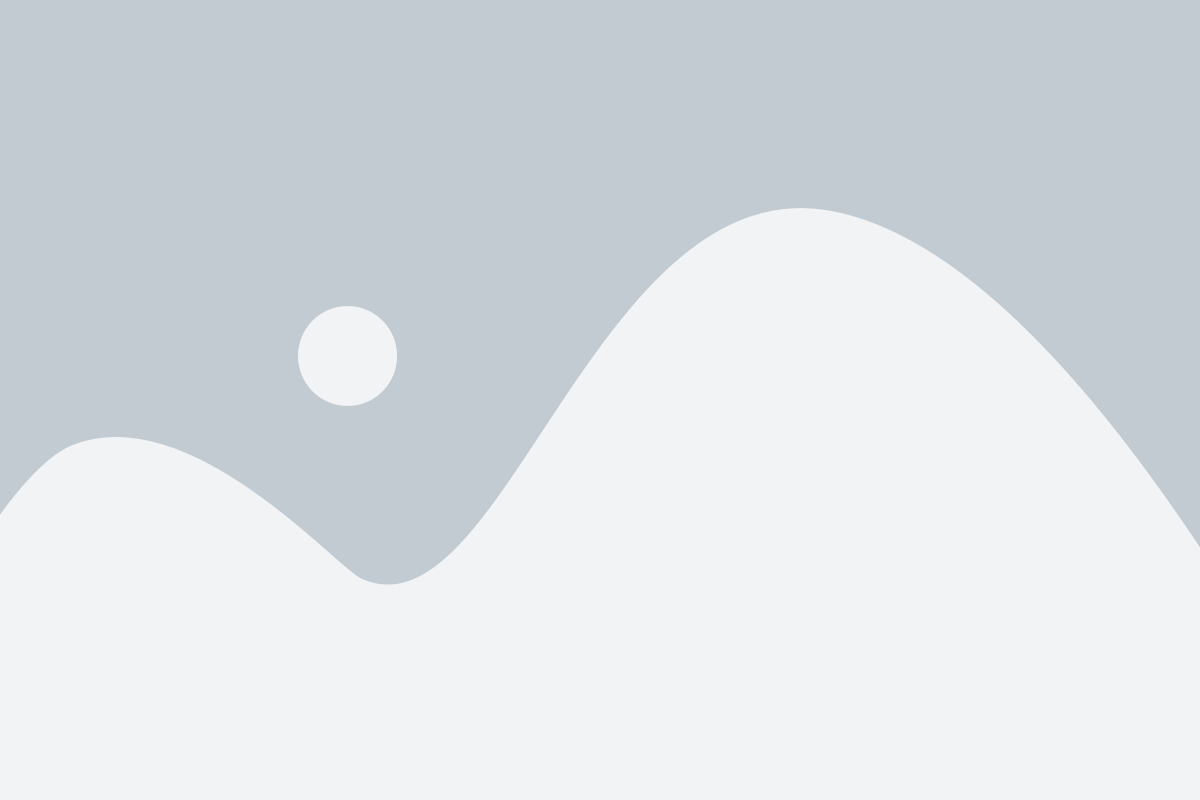
昭和23年3月22日愛媛県北宇和郡宇和海村戸島の城山(兼定が一時拠点としていたと伝承される)の松の大木が終戦直後に台風のため倒れたので戸島村では杣(そま)を雇って根元を引き切り処理の途中、その根元から大壷の割れたのが現れ其の中に古銭が沢山(合計で30貫あまり)あったという。
この3枚の古銭は戸島の古老から入手したものである。
江戸時代の数々の著作では兼定の素行が悪かったため、老臣どもが長宗我部元親と計って隠居を強制したことになっている。名かでも『土佐物語』は兼定の性行を軽薄、放蕩、好色の暴君とし、平田村の百姓源衛門の娘お雪との情事、それを諌めた忠臣土居宗算手討にしたことを大きく取り上げ劇的に書いているが、『元親記』矢『長元記には『行儀荒き人』とだけで、お雪とのことなど一行も書いていない。土居宗算手討の件も簡単に記しているだけで肝心の理由にはまったく触れていない。
作者不詳の「土佐物語」と違って、「元親記」の著者高島正重も「長元気」の筆者立石正賀も、ともに元親の旧臣で両記は元親の武功伝である。下克上の時世とはいえ恩義を受けた一条氏を滅亡に追いやった元親の立場を、少しでも良くするためには、兼定の悪い点は遠慮なく書けばよい筈である。それを書いていないということは「土佐物語」ほどの不行跡はなかったことになりはしないであろうか。特に老臣土居宗算手討の理由を書いてないことは、元親の旧臣である二著者にとって書きにくい事情、すなわち元親の立場を悪くする点があったためではあるまいか。これについて「四国軍記」が『元親は土佐七郡のうち六郡まで手に入れ、残るは幡多郡だけとなったものの、幡多の一条家には智勇すぐれた土居宗算が控えているので、容易に手出しができない。そこで計略によって宗算をなきものにすることを考え宗算に対して?々書状を送ったり贈り物を届けたりして、殊更に親密らしく見せかける態度をとった。宗算は迷惑に思ったが、元親の機嫌を損ねては一騒動起きずにはいないだろうと心配して穏忍していた。しかし間もなく思わぬ災難が宗算の身に降りかかった。宗算と元親が共謀して一条家に謀反を企てているとの噂が立ち、それを聞いて激怒した兼定に手討にせられた。これこそ元親の思う壺で、刃に血塗らずして幡多郡をとったり、と、ほくそ笑んだ。』ことが書いてある。おそらく、これが真相ではないだろうか。
事情はともかく、あたら忠臣を殺した兼定の短慮は経卒の誇りを免れない。このようなことがあったとすると、その頃の兼定の行状には常軌を逸したものがあったのは事実らしい。が、それも、元親の勢力が盛んになるにつれ、日に日に影の薄れゆく家運の挽回に悩み、自暴自棄になっての発作的な行為であったとすれば、一概に責めるのは酷な気がする。
主君兼定に隠居を迫り、若君内政に土佐一条五代を継がせ、長宗我部元親を後見役にしたことは主君の安泰を図るためで、家老と国侍の同意のもとに行われたのであったが、その後、為松・安並の二家老は国侍たちを軽蔑するようになった。これは憤慨した大岐・加久見・立石・江口・橋本・上山・伊予木・和田・小島・依岡などの国侍は連合してニ家老を襲撃した。剛勇のニ家老も思いがけぬ急襲を防ぎかねて自刃して果てた。
国侍たちの横暴家老打倒は彼等の溜飲をさげるには役立ったものの、結果的には一条家の衰亡を早めることになった。内乱の起こるような幡多郡に幼少の内政を置くことは後見人として許せないと、元親は自分の居城岡豊に近い大津城に内政を移し、中村城へは実弟の吉良左京進親貞を入城させた。こうなっては国侍たちも元親に従うほかはなかったであろう。それが戦国の世の習いでもあった。それでも中には元親に降ることをいさぎよしとしない者(伊与田・奈良・安宗・竹葉など)もあったが小島出雲守・依岡左京進に攻められ、あるいは殺され、あるいは逃亡した。小島・依岡はその功によって元親から多分の賞を受けたというから人の心は様々である。
かくて、公家大名土佐一条氏の実験は、長宗我部元親に完全に握られる事になったのである。
■ 兼定の中村退去
兼定は出家したのち(天正2年と伝えられている)(天正二年とされている)中村御所を出て九州豊後に渡っている。母の弟であり妻の父である大友宗麒を頼ったものであることは確実であるが、詳しい事情はわからない。「長元記」は、『御家門様(兼定)は豊後大友御母方の』御一類たるにより是の方へ送り申すなり。』と記し、『元親記』は、『下田の船本へ功送り豊後へ送り捨て申す。』と書いてあいる。いづれにしても追放されたことになるようである。
ここで考えてみたいのは、元亀4年から天正2年までの三年間に家臣が主君を隠居させたり、国外に追放するなどのことが実際に行われたであろうかということである。既に述べたように、その頃は京都から一条内基が来て中村御所に滞在中である。いかに兼定が不行跡であったにせよ、賓客の滞在中にそのような大それたことが行われたとは思えない。それで次のようなことが考えられる。
内基は中村に来てみて、国内の情勢にも家中の空気にも不穏なもののあるのを感じ、大事を未然に防ぐ方法として、兼定の隠居と心身静養のための豊後行きを勧めた。兼定もこれを了承して実行し、天正2年12月13日内政が従五位上、左近衛少将に叙任されて一応土佐一条氏の危機を脱することのできたことを見届けたうえ、翌3年5月安心して帰京したことであろう。(内政の叙任は「歴名土代」内もとの帰京は「公卿補任」に拠る)
兼定が豊後へ渡ってからのことについては「長元記」は全く書いてなく、「元親記」の『大友殿は一条殿の舅にてありけれども落人となり給ふ故か許可なく、又予州の地へ送返されるなり』とは余りにも無情な仕打ちで信じられない。それに反して兼定の不行跡を強調している「土佐物語」に『宗麒大いに驚き、扨(さて)も無念の事共かな、御心安く思召されよ、頓に本懐遂げさせ奉らん・・・・・』とあるのは意外である。「四国軍記」も『宗麒よきに労り奉りて仮の屋形を構え、無二の志をなしければ・・・・』と書いている。当然なことであろう。以上の著作の記事は何れも想像であろうが、キリシタン文献についてみても宗麒の厚遇を受けた事は事実のようである。
豊後に渡ってからの兼定については主としてキリシタン文献に拠って述べることとしよう。一口にキリシタン文献といっても、クラッセの日本西教史は史料取り扱いに欠陥があり、物語的に想像をめぐらしていて現在の学界では余りに用いられない(日本歴史大事典)。シュタイフェンのキリシタン大名記も、明治37年の刊行で江戸時代の著作を引用しているので誤りを冒している。信用できるものはカプラルの豊後通信(耶蘇会士日本通信豊後篇)と、フロイスの日本史(天正10年起稿、同14年完稿で天文18年ザビエル来朝から天正6年までの記録)、ヴァリニァーニの日本要録(スマリオ)がある。以上の三人は兼定に面接した人々であるから、兼定から過去のことを直接聞いている。ただし、その記事に多少の相違点のあるのは、兼定の話し方も時により表現の強弱があり、聞く方の受け取り方も人により違ったためであろう。[本以下の記述は松田毅一氏著「キリシタン研究」第1部四国篇と、松田毅一・佐久間正両氏編訳「日本巡察記/バアニャーノ」に拠るところが多い。]
■ ドン・パウロ
豊後に渡った兼定は大友宗麒の保護を受けて、臼杵の城下で3,4ヶ月を送るうちに、キリシタンになることを決意した。宗麒がキリシタンの援助者であった関係で、兼定も宣教師たちと交わっているうち、不運に悩む心の救いを異国の宗教に見出したためであろう。兼定は直ちに洗礼を受けたいとカブラル神父に願ったが、カブラルは『神の教えを十分了解するまで待つように」とすすめた。
そのころキリシタン大名は珍しくなく、公家でも清原枝賢があったとはいえ、兼定のように高貴な身分の人の例はなかったし、キリシタンの保護者である大友宗麒でさえも、未だ受洗していなかった(宗麒の受洗は天正6年)ことなどからカブラルの慎重な態度となったものと思われる。それでも弟子のバウチスタに対しては「もし一条殿が病気にかかるとか、帰国するようになった時には、すぐ洗礼を授けるように」と命じて肥前ノ国に旅立って行った。
だが、兼定受洗は間もなく実現した。幡多の有力な旧臣たちの懇情に応じて、急に帰国することになったので」、バウチスタから洗礼を受け、ドン・パウロの零名授けられた。天正3年(1575)のことである。
■ 渡川の合戦
幡多郡を回復して、愛と平和の理想郷建設の熱意に萌えるドン・パウロの兼定の一行は、大友宗麒の好意による数艘の軍船に、十字架の旗をなびかせて豊予海峡を渡り、伊予西海岸の法華津に上陸した。法華津城主法華津氏は土佐一条氏から幡多西部(宿毛市など)で多くの土地を与えられ、中村御所に近い不破村や宇山村にも給地を持っていた程であったから大いに兼定を歓待し幡多回復を応援することになった。これに力を得た兼定は、範延をはじめ御庄越前守・津島宗雲などの伊予西南部の将兵に護られ、国境を越えて幡多路に進入すると、兼定を慕う幡多の武士たちも馳せ集まって、先ず宿毛付近を回復した。目指すは中村であるが、中村に入るには国内第一の大河四万十川を渡らねばならず、中村城には土佐一条氏圧迫の主謀者吉良左京進親貞が控えているので容易でなかった。それでとりあえず西部でキリシタンの説教を始める準備を進めることになった。それを知った僧侶たちは大いに驚き、兼定撃退を元親に嘆願した。それでなくても兼定の帰国を喜ぶはずのない元親は、大軍を率いて岡豊から中村へ駆けつけた。一条勢も兵を揃えて具同栗本城に進出し、四万十川を挟んで一戦を交えたが衆寡適せず遂に敗れて伊予に退かねば成らなかった。これが世にいう渡川合戦である。(渡川とは四万十川の中村付近での俗称である)。
渡川合戦は土佐一条氏が興亡を賭けた大合戦と伝えられているけれども、実は小ぜり合い程度の戦いではなかったろうか。旭日昇天の勢いにある長宗我部元親に対して、斜陽族の一条兼定が寄せ集めの兵を持って対戦したところで、とうてい勝目のあろうはずがない。伊予の諸将が同情的に応援したとしても自身の危険を冒してまで兼定に尽くさねばならぬ義理はあるまいし、恩義を感じる幡多武将たちにしても、より強いものに付いて自家の安泰と本領安堵を図ることが処世の要件と割り切って考えねばならぬ時世である。負け戦を承知の上で大合戦をしたとは、どうしても考えられない。薄情のようであるが、主君を殺してその地位を奪うことさえ当然とした下克上の時代である。例え申しわけ的であったにせよ、旧主兼定の帰環を援けて一戦を試みたことは賞賛されてよいと思う。
■ 孤島に逝く
幡多回復の望みも、平和京建設の夢も空しく消えて、伊予宇和島港外の孤島「戸島」に敗残の身を隠した兼定に、不幸は尚も襲いかかった。長宗我部元親は、豊後の大友から兼定応援の軍勢が来るかも知れないと思い、事前に兼定を殺害することを考え、兼定とは特別に親しい小姓の一人(土佐物語や四国軍記では入江左近、元親記では入江兵部将輔となっている)を買収して実行させることにした。小姓はある夜熟睡中の兼定に斬り付け、兼定が深手のために失心しているのを絶命したものと信じて遁走した。兼定は重症ではあったが一命は取り止めることができたものの、医師の居ない島のことで恢復がはかどらず、ついに片腕を失い不具病弱の躰になってしまった。それでも、すべては神の御胸によるものと考え、キリシタンとしての信仰を捨てず、豊後の神父や司祭たちと文通することによって自らを慰めた。そうした不遇な生活にあった兼定が、ドン・パウロという一キリシタンとして最大の喜びは、天正9年(1581)の夏、イエズス会東印度管区巡察師ヴァリニャーノに面接できたことである。ヴァリニャーノは天正7年(1579)来朝して九州を巡察したのち、天正9年(1581)京都にのぼり、織田信長の歓待を受け、畿内の教会を歴訪して、8月から9月にかけて土佐沖を航海し、豊後に帰ったのであるが、その途中ドン・パウロを慰めることにした。知らせを受けた兼定は大いに喜び、6人の家臣連れ小船に乗って面会に赴いた。その時、兼定はキリシタンの人々と生活のできないこと、島の人々をキリシタンに改宗させる力のないことを嘆き、自分が死んだときにはキリシタンの儀式によって葬ってもらいたいと述べた。ヴァリニャーノは兼定を慰めて別れ翌年日本を去った。
兼定は天正13年(1585)7月1日、熱病のために42年の不運な生涯を閉じた。その後間もない8月6日、長宗我部元親は豊臣秀吉に降伏し、ようやく手に入れた阿・讃・予の三国を没収されている。思えば不思議な運命の巡り合わせである。
兼定の歿年は従来の説では天正3年となっていたが、キリシタン文献と高野山成福院の過去帳とによって、天正13年であることが判明した。墓は戸島に在るが、兼定の希望であったキリシタンとしては葬られていない。形の崩れた宝篋印塔が、小さな祠の中に祭られているのは哀れである。それでも、今なお島民の参詣が多いことで、兼定の霊魂は慰められることであろう。
| トップページ | 歴史ロマントップページ |
